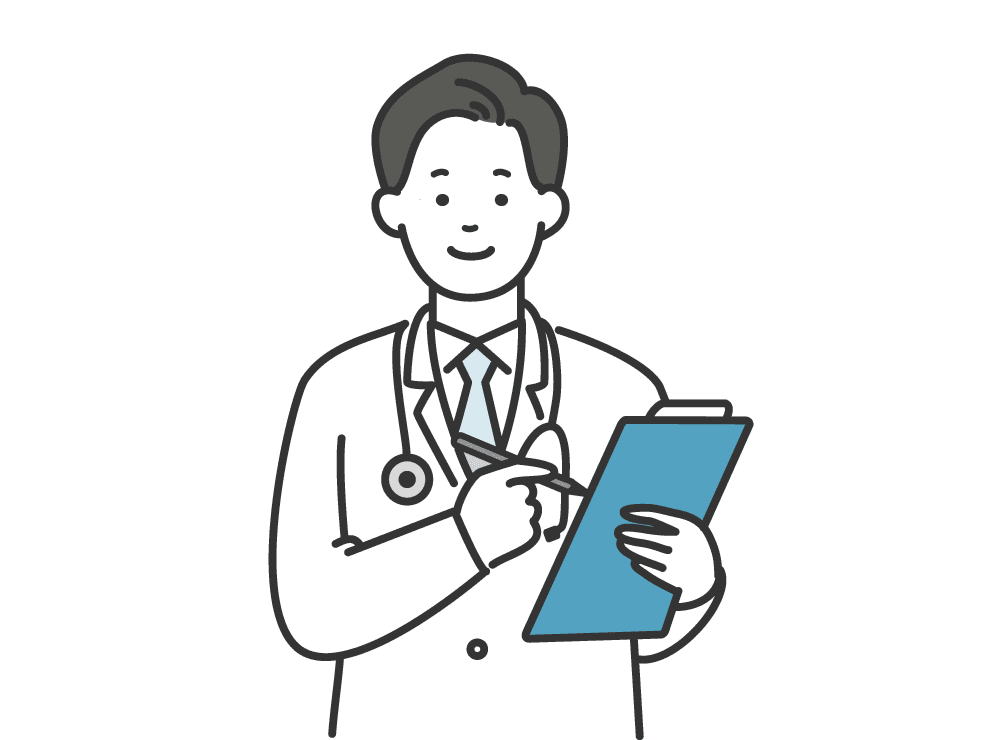便秘とは

便秘とは、「便がなかなか出ない」「出にくい」状態をいいます。
一般的には「週3回未満の排便」または「5日以上便が出ない」場合に便秘と考えられます。
また、毎日排便があっても排便時に痛みが強い・出血がある場合も便秘に含まれます。
腸に便がたまりすぎると、逆に少量の便が漏れ出てしまうことがあります。
そのため、1日に何度も少しずつ柔らかい便やコロコロとした便が出る場合も、実は隠れた便秘のサインです。
このように治療が必要な状態を「便秘症」と呼び、1〜2か月以上続くと「慢性便秘症」とされます。
小児の便秘症は珍しくなく、10人に1人以上に見られるといわれています。
特に以下のような生活の変化がある時期に起こりやすい傾向があります。
- 離乳食の開始・終了期
- トイレトレーニングの時期
- 入園・入学など新しい生活環境が始まったころ
適切に治療を行えば、多くのお子さまは数日〜2か月ほどで「週3回以上・スムーズな排便」を取り戻せます。 その状態を維持できれば、1〜2年のうちに自然に便秘症が治ることも少なくありません。 ただし、再発しやすい病気でもあるため、改善しても症状が戻ったときは自己判断せず早めに受診することが大切です。
子どもの便秘の原因
子どもの便秘症は、体の発達や生活習慣、心理的要因など複数の要因が重なって起こります。
「痛い記憶」が悪循環を生む
硬い便を出すときに肛門が切れて強い痛みを経験すると、小さなお子さまは「うんちをすると痛い」と覚えてしまいます。 その結果、次の便意を感じても我慢するようになり、肛門をきつく締めてこらえたり、足を交差させて我慢する行動がみられるようになります。
便を我慢している間に大腸は便の水分を吸収し、便はますます硬くなります。 「痛い → 我慢 → 便が硬くなる → さらに痛い」という悪循環が続くと、便秘はどんどん悪化します。
また、腸に便が長くたまることで直腸が鈍くなり、便意を感じにくくなることもあります。 これにより排便のタイミングを逃しやすくなり、さらに便秘が進行します。
このように、体と心の両面の悪循環が子どもの慢性便秘の大きな原因となります。

便秘症の診断
診断はまず、便の回数・硬さ・排便時の様子などを詳しくおうかがいする問診から始めます。
必要に応じて、レントゲン撮影や腹部エコー検査などを行い、腸の状態を確認します。

便秘と判断される目安
- 便の回数が少ない(週3回未満、または5日以上出ない)
- 排便の際に強くいきむ、痛がる、出血がある
- 少量ずつ何度も出る・柔らかい便が漏れる
このような場合、腸の中に多量の便がたまっていることがあります。
1〜2か月以上続く場合は「慢性便秘症」と診断され、治療が必要です。
一方、一時的に出にくくなっただけの「一過性便秘」であれば、浣腸や一時的な薬で改善します。
慢性便秘症と診断された場合には、腸やホルモン、神経の異常など他の病気が隠れていないかも確認します。
必要に応じて追加検査や専門医療機関への紹介を行います。
主な治療方法
治療の目的は「便をスムーズに出せる状態を整え、排便習慣を身につけること」です。
生活習慣の工夫と薬の併用で、多くのお子さまは改善します。
生活習慣の見直し
- 毎日決まった時間にトイレに座る(特に朝食後が効果的)
- 規則正しい睡眠・食事・運動リズムを整える
食事の工夫
- 水分をしっかりとる
- 野菜・果物・海藻・穀物など食物繊維を多く含むバランスのよい食事
運動習慣
- 外遊びや軽い運動を毎日の生活に取り入れることで腸の動きが活発になります。
薬による治療
- 生活改善だけで改善しない場合は、便を柔らかくする薬(浸透圧性下剤など)や整腸剤を使用します。
- 硬い便が多くたまっている場合は、浣腸を行うこともあります。
- 薬は「便を出しやすくする補助」と考え、必要な期間のみ安全に使用します。
ご家族へのメッセージ
子どもの便秘は「がまん」や「食べ過ぎ」が原因ではなく、成長や体のバランスの変化によって起こるよくある症状です。
早めに相談してあげることで、つらい思いをせずに改善できます。