「怠けている」「朝に弱い」と
誤解されやすい病気です

起立性調節障害とは、自律神経の働きがうまく調整できず、立ち上がったときに血圧や脈拍のコントロールが乱れることでさまざまな症状が出る病気です。
思春期前後のお子さまに多くみられ、下記のような症状が特徴です。
- 朝なかなか起きられない
- 立ち上がるとめまいや立ちくらみがある
- 体のだるさや頭痛、食欲不振が続く
一見すると「怠けている」「生活リズムが乱れている」と誤解されやすいのがこの病気の難しいところです。
しかし、起立性調節障害は心の問題ではなく、自律神経の未成熟によって起こる身体の病気です。
特に思春期は成長やストレスの影響で自律神経が不安定になりやすく、学校生活や人間関係の変化で症状が強く出ることもあります。
正しい診断と生活習慣の工夫(睡眠・水分・塩分・軽い運動など)、必要に応じた薬物療法で、多くのお子さまは少しずつ回復していきます。
主な症状
- 朝なかなか起きられず、午前中に強い倦怠感がある
- 立ち上がるとめまいやふらつき、動悸を感じる
- 頭痛・腹痛・吐き気・食欲不振が続く
- 午後からは比較的元気になることが多い
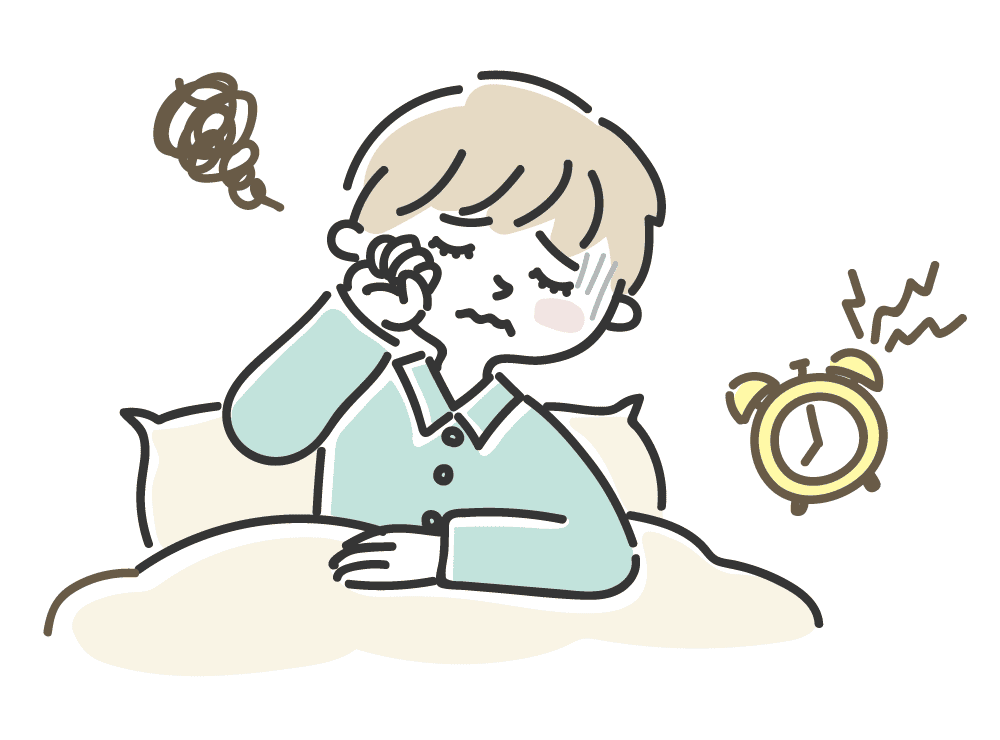
起立性調節障害の原因
起立性調節障害は、「生活習慣の乱れ」だけでなく、自律神経の働きが未成熟でうまく血圧や脈拍を保てないことが主な原因です。
自律神経は血圧・脈拍・体温などを自動的に調整し、体を安定させる重要な機能を担っています。
思春期には体の成長に伴ってこのバランスが崩れやすく、特に「立ち上がったときに血圧を保つ力」が弱くなることで症状が出やすくなります。

主な要因
- 成長期特有の変化
・急激な身長の伸びなど、体の成長に血液循環が追いつかず、自律神経が不安定になります。
- 自律神経の未成熟
・思春期の子どもは自律神経の発達途上にあり、血圧や心拍のコントロールが十分でないことがあります。
- 精神的・環境的な影響
・学校生活・友人関係のストレス、生活リズムの乱れ、睡眠不足などが症状を悪化させることがあります。
- 体質的な要素
・もともと血圧が低いお子さま、または家族に同じ症状の経験がある場合に起こりやすい傾向があります。
診断について
診断はまず、症状や生活リズムを丁寧にうかがう問診から始まります。
「朝に弱い」「立ちくらみがある」「午後から元気」などの特徴的なパターンを確認します。

主な検査
- 起立試験
・横になった状態から立ち上がった際の血圧・脈拍の変化を測定し、自律神経の働きを評価します。
- 心電図・血液検査
・他の疾患が隠れていないかを確認します。
起立性調節障害は、一般的な健康診断や血液検査だけでは異常が見つかりにくいため、症状と検査結果を総合的に評価することが重要です。
また、学校生活や登校状況への影響も大きいため、必要に応じて学校と連携し、無理のない対応を検討します。
主な治療方法
起立性調節障害の治療は、薬だけに頼らず、生活リズムの改善と環境調整を中心に行うことが大切です。
お子さまの体質や症状に合わせて、段階的に取り組みます。

生活リズムを整える
- 規則正しい睡眠・起床を心がける
- 朝起きづらくても、少しずつ決まった時間に起きる習慣をつける
食生活の工夫
- 朝食をしっかり食べる
- 水分を多めにとる(1日1.5-2L)
- 塩分を適度に摂取し、血圧を保つ
適度な運動
- ウォーキング、ストレッチ、軽い筋トレなどで血流を促し、自律神経を整える(立っての運動がむずかしいときは座ってこげるエルゴメーターなど)
環境の調整
- 学校・家庭での理解と協力が不可欠です。
無理のない登校時間や活動量を一緒に考えていきます。
薬物療法
- 生活改善だけで症状が強い場合には、血圧を安定させる薬や自律神経を整える薬を使用することがあります。
- 症状や体調をみながら、安全に段階的に進めていきます。
ご家族へのメッセージ
起立性調節障害は「怠け」や「やる気の問題」ではなく、成長期に起こる自律神経のアンバランスによる身体の病気です。
早めに正しく理解し、焦らず向き合うことで、多くのお子さまは回復していきます。
ご家庭・学校・医療が一緒になって支えることが、お子さまの笑顔を取り戻す第一歩です。



