日本アレルギー学会専門医が、
アレルギー疾患全般に対応します

当クリニックでは、日本アレルギー学会専門医が、アトピー性皮膚炎・食物アレルギー・アレルギー性鼻炎(花粉症)・気管支喘息など、幅広いアレルギー疾患を診療しています。お子さまやそのご家族の年齢や生活スタイルに合わせて、最適な検査・治療・生活指導をご提案します。
「せきが長引く」、「季節の変わり目にくしゃみや鼻水が止まらない」、「特定の食べ物でじんましんや体調不良が出る」、こうした症状の背景には、免疫が過剰に反応するアレルギーが隠れていることがあります。放置すると生活の質(QOL)が下がるだけでなく、重症化する場合もあります。早めの診断と適切な管理が大切です。
当クリニックでは、必要な検査で原因を見極め、吸入治療・内服薬・スキンケア・環境整備・食事指導などを組み合わせて総合的にサポートします。特に小児では、成長・発達への影響に配慮し、無理のない治療計画を一緒に作っていきます。病気のしくみや治療法は、保護者にもわかりやすくご説明し、ご家庭での工夫も具体的にお伝えします。
気になる症状があれば、お気軽にご相談ください。地域のかかりつけ医として、皆さまの健康をしっかり支えます。
『アトピー性皮膚炎』について
アトピー性皮膚炎は、強いかゆみを伴う湿疹がよくなったり悪くなったりを繰り返す慢性の皮膚疾患です。皮膚のバリア機能低下により、乾燥や汗、ダニ・ハウスダスト、花粉などの刺激やアレルゲンが侵入しやすくなり、炎症とかゆみが続きます。かきこわしは悪循環を招くため、早めのコントロールが重要です。
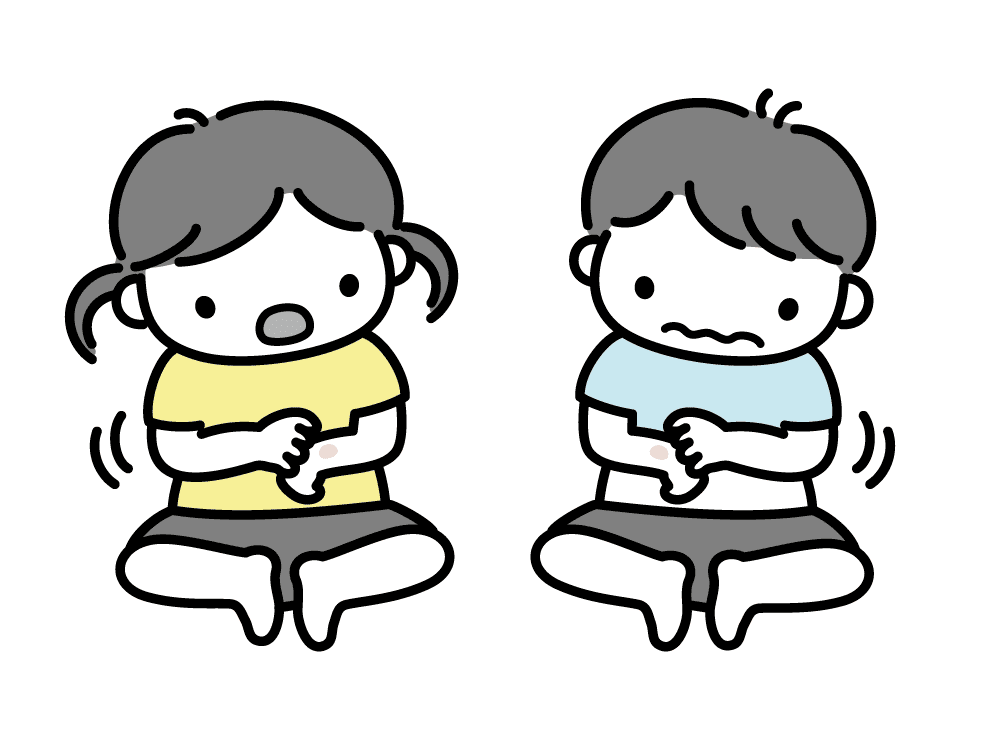
アトピー性皮膚炎の治療の基本(4本柱)
- 悪化因子への対策
・乾燥・汗・ほこり・花粉・ダニ・ストレスなどを可能な範囲で回避
- スキンケア
・毎日の十分な保湿でバリア機能を補強
- 薬物療法
・炎症がある部位に外用薬(ステロイド外用薬が治療のメインですが昨今はステロイド以外の良い薬も増えてきました)を適切に使用。
- 再発予防:プロアクティブ療法
・症状が落ち着いている時期も、週数回の外用を継続して再燃を予防する方法です。良い状態を長く保てます。
重症例への対応
- 外用・内服で不十分な場合は、生物学的製剤(例:デュピルマブ等)などの選択肢があります。適応や安全性を丁寧に評価し、必要時は高次医療機関と連携して最適な治療につなげます。
『食物アレルギー』について
食物アレルギーは、特定の食物に触れたり食べたりした後に、じんましん・かゆみ・腹痛・嘔吐・下痢・せき・喘鳴などが現れる病気です。まれにアナフィラキシー(全身反応)を起こすことがあり、迅速な対応が必要です。
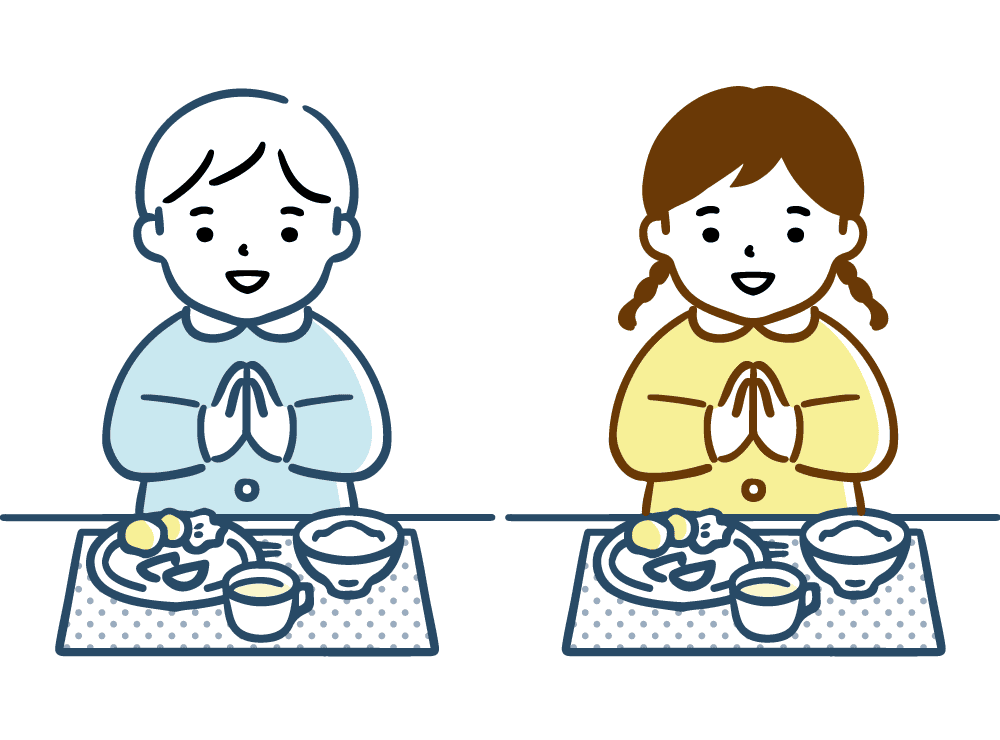
診断と管理
- 詳細な問診と必要な検査(特異的IgE検査 など)を組み合わせて原因食物の推定を行い、必要時経口負荷試験を行います。
- 過度な除去は栄養リスクになるため、栄養バランスを考慮しながら必要最小限の除去にとどめます。
- 症状に応じて内服薬を処方します。アナフィラキシー歴や高リスクの方にはエピペン®の処方・使い方指導を行います。
- 園や学校提出用の指示書や連携もサポートします。
※経口食物負荷試験や経口免疫療法については、適応・安全体制を踏まえ、院内または連携機関で実施可否を判断します。
『アレルギー性鼻炎(花粉症)』について
花粉・ダニ・ハウスダスト・カビ・ペットの毛などのアレルゲンで、鼻水・鼻づまり・くしゃみを繰り返す病気です。
小児では鼻づまりが続くと、睡眠・集中力・学習、さらには口呼吸による歯並びや発育にも影響し得ます。早期診断・適切な治療が大切です。

治療のポイント
-
環境対策
・寝具のダニ対策、換気・掃除、花粉飛散時の対策 など
-
薬物療法
・内服抗ヒスタミン薬、点鼻薬 などを症状に合わせて調整
-
アレルゲン免疫療法(舌下免疫)
・薬で十分にコントロールできない、または根本的治療を希望される場合に検討します(スギ・ダニなどが対象)。開始時期や適応を丁寧にご説明します。
『気管支喘息』について
気管支喘息は、気道に慢性的な炎症が続き、咳・喘鳴(ヒューヒュー/ゼーゼー)・呼吸困難を発作的に起こす病気です。夜間・早朝・運動後に悪化しやすいのが特徴です。小児では、かぜの後に喘鳴が目立ち、直ちに喘息と断定できないこともあります。症状が続く場合は、ご相談ください。
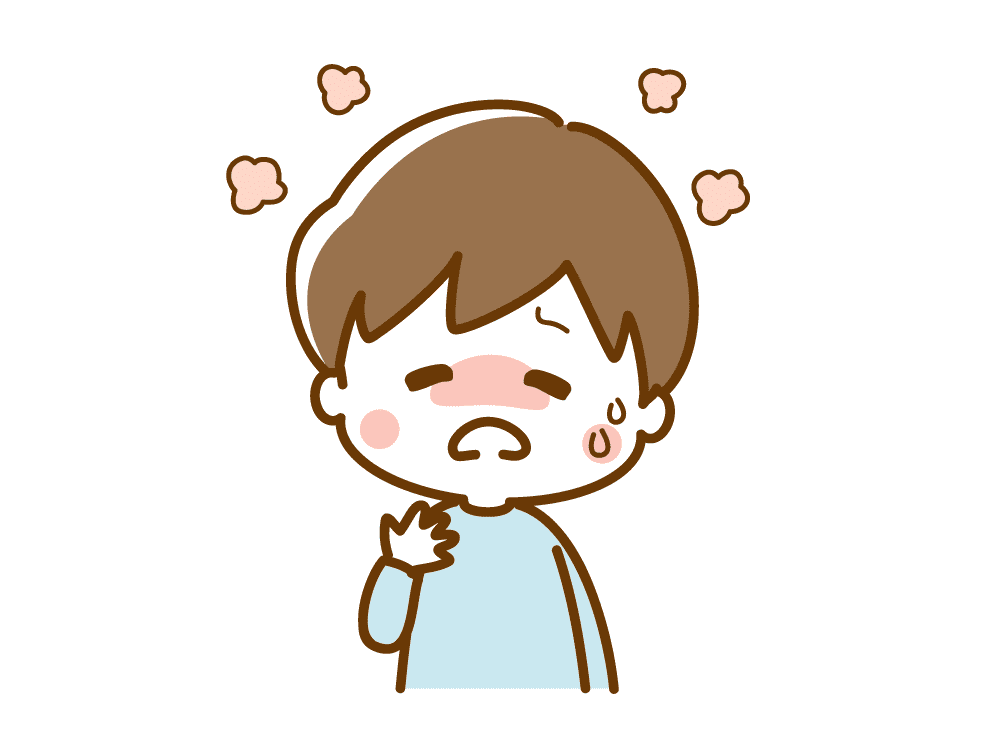
気管支喘息の診断
-
丁寧な問診
・夜間・早朝の咳、運動や天候・ダニ・花粉で悪化するか、家族歴(喘息・アトピー・花粉症)や生活環境(ダニ・ペット等)
-
必要な検査
・血液検査(特異的IgE 等)、呼気NO(気道炎症の指標)、胸部X線、肺機能検査 など
- 問診と検査を組み合わせ、悪化因子の把握と回避まで含めた総合評価を行います。
気管支喘息の治療
-
発作時治療
・気管支拡張薬で呼吸を楽にします。
-
長期管理
・再発・悪化を防ぐため、吸入ステロイド薬を基本とした治療を継続します。症状に応じて気管支拡張薬との合剤などを段階的に調整します。
- 吸入ステロイドは局所作用が中心で全身性副作用は少ないとされています。正しい手技・用量で安心して継続することが重要です。
- 成長・生活リズムに合わせて個別化し、季節・運動・感染流行などに応じてステップを調整します。吸入指導やアクションプラン(発作時の対応表)もお渡しします。


